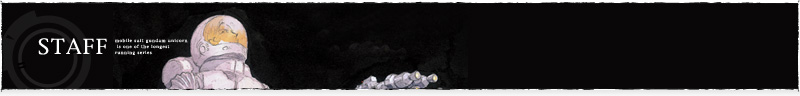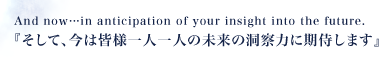ナビゲーションエリア
メインコンテンツエリア
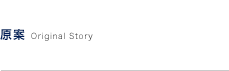 |
|
かつて、エンドマークの代わりにこんな言葉を観客に投げかけたフィルムがあった。いまから三十年近く昔の話だ。

“可能性”について語ったフィルムだった。いや、ドラマの中身だけではなく、その存在自体が“可能性”だと言えた。「たかがロボットアニメ」がドラマを語り、若者たちの熱狂的支持を取りつけ、ついには三部作の劇場公開作品になってしまった。それは「人とフィクションの関係性」そのものが変化してゆく兆しでもあり、その熱をもって劇中のドラマを−−人の革新についての物語を、観る者に納得せしめる勢いがあった。
当時、まだ若者たちと括られるほどの年齢にも達していなかった我々は、そうして複合的に提示された“可能性”の中に現実の未来を重ね合わせ、言語化もままならない茫洋とした期待感に酔った。洞察力、なんて難しい単語も必死に覚えた。あのメッセージをもって作品は完結したが、“可能性”をめぐる戦いは現実の我々に引き継がれた−−子供ながらにそう感じ、昨日のくり返しではない明日の到来を信じたからかもしれない。
そして、いま−−我々は大人になった。歴史はくり返すと肌身で学び、可能性より確実性を選び取るのを常とし、ビジネス・スキームという筋道が立たなければなにも始められない大人になった。“可能性”に心震わせた感性は幼少期のノスタルジーと一緒くたになり、未来には期待より不安を感じることの方が多い。だからこそ、ノスタルジーに逃げ場を求め、三十年前のフィルム(と、その派生品)を飽かず眺めたり、関連商品に大枚をはたいたりしている。
それをして、あの時に観た“可能性”が花開き、“市場”を形成したのだと結論づけることもできよう。しかし我々があのフィルムの中に見出した“可能性”とは、そんなものだったか? いま再びDVDで追体験した時、心の奥底でどよめく塊はノスタルジーだけのものか? いや、もっと具体的な話をしよう。いま、我々が玩具会社や放送局に勤務する中堅社員だった時に、あのフィルムの存在を容認できるだろうか? わかりにくい、マーケットの目算が立たないと難癖をつけ、企画が持つ“可能性”を圧殺しているのではないか?

ノーと言いきれる人はいまい。いたとしたら、友としては尊重するが、仕事仲間としてはおつきあいできないかもしれない。残念ながら、それが大人の世界だ。そしてそのような世界で呼吸をしながら、あの時の“可能性”に魅せられ、その先を見てみたいと希望するのも我々なのだ。
ならば、間違ってもいい。もう一度“可能性”を追求してみようではないか。ノスタルジーに浸ることなく、あの“可能性”の行き着く先を直視してみようではないか。
続編がすでに語っている? そうかもしれない。しかしそれらは、当時若者であった我々に幻想との決別を促すものだった。我々の答はまだ出ていない。あのラストメッセージに託された「期待」は留保されたままだ。
いま、我々は十分に大人になった。だから大人の言葉で応えよう、“可能性”を示した先達たちの思いに対して。現在におもねることなく、市場という言葉に振り回されることなく。あのフィルムと同じ地平に立ち、大人だからこそ語れる事々を語ってみせよう。
ノベライズではない、文芸発の新『ガンダム』。複合的な展開も視野に入れた本プロジェクト自体が、ガンダム世代と呼ばれる我々が仕掛ける“可能性”だとも言える。未知のスキームの先行きは決して平坦ではない。だが我々には勝算がある。最強のスタッフが集まってくれたからだ。今後、追々明かされるその陣容を知れば、勝算といった我々の言葉の意味を理解してもらえるだろう。
とはいえ、その成否の鍵は読者ひとりひとりの手に委ねられている。ファンの力なくして、「ファーストの奇跡」は起きなかった。これから始まる物語に共感の余地あれば、ぜひ力を貸してほしい。その力が得られてこそ、本作はガンダム市場という限定された枠を飛び越え、社会に対し、未来に対し、ガンダム世代の“可能性”を伝える声となる。
そう、戦いは引き継がれたのだ。それゆえ、最後にあのフレーズをくり返そう。同じ目線から、いっそうの切実さをもって。
『我々は、生き延びることができるか−−』
<角川書店 『月刊ガンダムエース』2006年12月号より転載>
福井 晴敏
コピーライト エリア